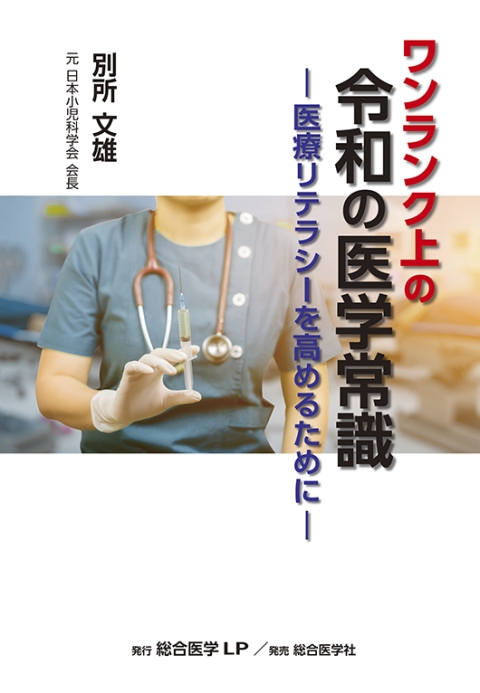トップ / 好評書籍・おすすめ
ワンランク上の 令和の医学常識 —医療リテラシーを高めるために—
商品説明
- 300
- 四六
- 1,600
- 2023年7月
巷に氾濫している健康に関する情報は玉石混交であり、自分に必要な情報を見極めて最善の選択をすることが必要です。本書はこの知識の拠り所となるもので、正しい知識を習得することで健康な生活を送ることができます。
I.病気と医療のリテラシー
1.病気とは何か
- 「病気」は、どう考えられてきたか
- (a)古代から中世までの考え方
- (b)中世から近代までの考え方
- (c)近代以降は、精神面も配慮されるようになった
- なぜ病気になるのか
- (a)微生物は最強の環境因子
- (b)今やヒトそのものが重要な環境因子
- ヘルスプロモーションという考え方が重要
2.診断とは、健康状態や病状を判断すること
3.治療とは、病気の状態を元の健康な状態に戻すこと
- 治療の目的・目標
- 治療には4つの原則と形式がある
- (a)自然治癒力による治療
- (b)原因の除去(原因療法)
- (c)症状の除去・軽減(対症療法)
- (d)機能の回復や残存機能の向上
- (e)「治療効果の評価」には、心の働きにも留意が必要
4.予防にはどんな方法があるか
- 清潔な水の供給をはじめとする環境整備の重要性
- 体質の改善・強化の大切さ
- (a)食事は、5大栄養素をバランス良く
- (b)運動は、タンパク質の糖化を防ぐ
- (c)睡眠は、生活の質を左右する
- 予防接種は有効なのか
- (a)予防接種の利点と注意点
- (b)予防接種のワクチンには4種類ある
- 早期発見・早期治療(疾患スクリーニング)
- (a)がん検診には、いくつかの問題点がある
- 神経芽腫のスクリーニングはなぜ中断されたか
- (b)医療技術の評価と意義
5.知っておきたい「基礎知識」としての医療リテラシー
- 歴史から見た人類と医療
- 西洋医学と東洋医学の大きな違い
- 「薬剤」は何がどのようにして「薬剤」となったか
- 鍼治療の効果測定の難しさ
- インド医学を西洋医学から見ると
- 民間薬、健康食品、サプリメント
- (a)医薬品・健康補助食品は、どのように分類されるか
- (b)メタボリックシンドロームは、なぜ怖いか
- (c)果糖は、何から摂るかが重要
- ・果糖は、果物から摂りたい
II.人体の仕組みと働きについてのリテラシー
1.体内を一定に保つには、エネルギーが必要
2.エネルギーは、グルコースを酸素に結合させて獲得する
3.酸素は、血流によって、脳や心臓などの臓器に運ばれる
4.消化管の働き
- 消化と吸収の仕組み
- 腸内は細菌だらけ
- 腸に住み着いている細菌(腸内細菌叢〈腸内フローラ〉)の総量は1・5㎏
- 便をじっくりと観察してみよう
5.呼吸器の働き
6.循環器の働き
7.腎臓・泌尿器系の働き
- ・腎臓は、生体内の海を管理している
- ・内分泌臓器としての腎臓
8.肝臓の働き
- (化学工場としての肝臓)
- (貯蔵庫としての肝臓)
- (肝炎と肝炎ウイルス)
9.膵臓の働き
- 膵臓の外分泌腺
- 膵臓の内分泌腺
10.運動器の働き
11.血液の働き
- 有形成分は、どこで作られるか
- (a)赤血球は、ヘモグロビンを入れる袋
- (b)白血球の種類とそれぞれの役割を知っておこう
- (c)血小板は、出血を止める
- 液性成分(血漿)には何があり、何をしているか
12.免疫の働き
13.内分泌の働き
- 間脳下垂体系によるホメオスターシスの維持
- (a)下垂体後葉は、体内の水分を調節する
- (b)下垂体前葉は、ストレスに対応したり、成長を促したりする
- 甲状腺—放射線と甲状腺がんとの関係―
- 副腎はデュアル臓器―髄質と皮質はすべてが異なる―
- 糖尿病は、失明や腎不全、末梢神経障害の原因ともなる
- 副甲状腺は、カルシウム代謝に関係するホルモンを分泌する
- その他の内分泌腺と存在部位
14.神経系は、皮膚と同じ起源を持つ
- 神経細胞の構造と機能は、コンピュータに似ている
- 神経系には、3つの「系」がある
- 脳は、領域によって機能分担している
- 脳の発達は、生まれてから1000日までが鍵
- 脳は、酸素やエネルギーの大食らい臓器
- 末梢神経は、機能的に2つに分けられる
- (a)体性神経は、運動神経と感覚神経に分けられる
- (b)自律神経系は、交感神経と副交感神経に分けられる
- 脳神経は、頭頸部の運動や感覚を扱う
- 感覚の仕組み
- (a)視覚―外部情報の80%は、視覚による―
- (b)聴覚と平衡覚を司る仕組み
- (c)味覚の成り立ち
- (d)痛覚は、主観的なものか
- (e)感覚の実体は、どこまで解明されているか
- 認知症―高齢者の5人に1人―
- (a)高次脳機能とはどんな機能か
- (b)記憶―感情とも繋がっている―
- 3歳以前のことも記憶されるのか
- (c)認知症の症状は、2つに分けられる
- (d)認知症には、治療可能なものがある
- 依存症と快感は、記憶と深い関係にある
- (a)脳内報酬系は、快感を作り出す
- (b)ハエもアル中になる
15.水と電解質は、浮腫や高血圧の原因として重要
16.がんは、死亡原因の第1位だが、高齢化と関係している
- どのようにして「がん」はできるのか
- 組織や器官の形成のされ方(発生学)
- 細胞の複製―複製の失敗は、「がん」の始まりだが、「進化」のためには必要―
- 複製の間違いの処理の失敗が「がん」の始まり
- がんに関する遺伝子は、「がん家系」や「若年性のがん」に関係している
- がんを発生しやすい体質は、遺伝する
- がんの発生要因―特に小児がんについて―
- (a)小児のがんは、「非上皮性」が多い
- (b)小児のがんの治療成績は、大変良好
17.中毒性疾患と公害を考える
- 公害は、慢性の中毒性疾患
- 慢性毒性では、生物濃縮からの健康被害も起こる
- 有名な中毒事件・公害を知っておこう
- (a)水俣病
- (b)新潟水俣病
- (c)イタイイタイ病
- (d)四日市公害
- (e)土呂久ヒ素公害
- (f)森永ヒ素ミルク事件
- (g)サリドマイド事件
- (h)PCBによるカネミ油症
- (i)SMON
- (j)大腿四頭筋短縮症
- (k)足尾鉱毒事件
- 農薬中毒―DDTから蚊帳へ―
- (a)除草剤化学兵器として使われた枯れ葉剤―
- (b)殺虫剤―蚊取り線香も油断がならない―
- 生物毒(微生物以外の有毒な生物)も知っておこう
- (a)食用植物と間違えやすい有毒高等植物とは
- (b)毒を持つ動物に注意
- (1)代表的な無脊椎動物は、毒グモ
- (2)脊椎動物では、フグと毒ヘビ
18.地球温暖化は、新興感染症に影響を与えている
III.医療の仕組みと医療制度を考える
- 「医学」と「医療」の関係は、「科学」と「技術」の関係
- (1)「医学博士」の肩書きは、診療の質には関係ない
- (2)「医学」、「医療」と「医術」
- (3)「医療法」と「医療現場」の乖離が問題
- (4)社会的な施策としての「社会保障」
- さまざまな医療職で構成された「チーム医療」
- (1)社会生活における心の取り扱いの重要性
- 患者の「心の取り扱いの重要性」が、やっと認められてきた
- (2)医療における専門分化の利点と注意点
- (3)医療供給体制と医療経済―医療は社会的共通資本―
IV.医療リテラシーを身につけよう
- メモ
- :衛生仮説と旧友仮説
- :ヘルスプロモーションに関連する国際的な宣言
- :プラシーボ効果(偽薬効果)およびノシーボ効果
- :3大感染症に対する国際支援
- :新しい学問としての疫学
- :肥満度(body mass index = BMI)の計算と必要エネルギーの計算
- :DOHaD = Developmental Origins of Health and Disease
- :睡眠障害
- :睡眠負債
- :副作用、副反応、有害事象
- :がん検診における2つのバイアス
- :医療技術の評価
- :WHOによる伝統的中国医学の公認
- :システマティック・レビュー
- :あるアミノ酸サプリ
- :果糖の代謝過程から見る果物の利点
- :エネルギーの産生と保存の過程
- :肺の表面活性剤としてのサーファクタント
- :たばこの煙には、高濃度の一酸化炭素が含まれている
- :腎臓で尿が作られる仕組みと尿崩症
- :アルコールの運命
- :2種類のビリルビン
- :骨の強度
- :鉄を多く含む食材は
- :チアノーゼがあっても必ずしも酸欠ではない!
- :酸素の毒性―有酸素運動は有害か
- :下垂体の発生を知ると病気の症状が分かる
- :先端肥大症と巨人症との関係
- :失楽園仮説
- :水と電解質の恒常性維持は、腎臓の大切な機能の1つである
- :遺伝の「優性」と「劣性」
- :発がんの2ヒット説
- :薬害・公害の発生要因と科学者の態度
- :3時間待ちの3分診察の本質